柳屋
木曾屋は大宮宿の仲町にある。仲町は名前の通りちょうど宿場の中ほどにあり、脇本陣が3軒、旅籠が5軒ある。脇本陣とは本陣の予備的宿で、本陣で大名の参勤などに対応しきれない場合に供される格式の高い宿である。
問屋場は仲町にもあるが、番頭の言っていた問屋場は北の方の宮町にある。問屋場の仕事は基本的には幕府や大名の交通のために人馬を継ぎ立てる事と、公用通信を届けることである。公用通信の運搬はいわゆる飛脚が運ぶ。だが、一般旅行者が増えてくるとそれにも対応するようになった。
宮町と仲町の間には大門町があり、ここには紀州鷹場北澤本陣がある。鷹場とは幕府が設定した鷹狩に設定した区域で、江戸城より5里四方を将軍家。それより外側を御三家の鷹場とした。北澤家はその紀州侯の鷹場の本陣であり、鳥見(鷹狩の準備などする)も兼ねていた。安永4年(1775)2月1日の大火ではここが火元となり85軒が焼失した。
千歳と幾が大宮に現れたのはこの大火の1月ほど経った頃。そう、ちょうど今頃だった。父親に連れられて旅をしていた姉妹が、まだ焼け野原だった大宮に来た時に、氷川神社の一の鳥居にある団子屋で倒れた。卒中だった。この父親に関しては謎多き人物だが、何者だったか今もってわからない。
突然孤児になってしまった姉妹を拾ったのは柳屋夫婦だが、その柳屋も焼失していた。私の父平太夫は店を失いながらも見ず知らずの子供を育てる柳屋夫婦を見て感激し、柳屋に再建資金を提供したのだ。そういう関係もあって柳屋と木曾屋は昵懇になったのだが、自然と姉妹も木曾屋に遊びに来るようになった。
姉妹が初めて木曾屋に来た時、平太夫は千歳に「何か欲しいものはあるか?」
と聞いてみた。それはごく自然に憐みから出た言葉だった。しかし千歳はまっすぐ平太夫の眼をみてこう言った。
「あたしが望むものをおまえ様がくれるなら、あたしはおまえ様の望むものをあげましょう。でも今じゃない。」
幼いながらその機知に富んだ答と気丈さに平太夫は圧倒された。平太夫がその後千歳に教養や芸事、経営学などあらゆることを叩き込むことになるのだが、それはこの時この少女に魅了されたからだ。
柳屋は宮町に入ってすぐのところにある。清五郎は店の前で立ち止まると寂しそうに屋号の看板を見上げた。柳屋が「十字屋」に変わっている。柳屋は千歳が自殺した後、利兵衛が完全に寝込んでしまい、経営が出来なくなって店ごと売り払った。病身の利兵衛は木曾屋で引き取ったが、柳屋の借金は千歳の2年余りの経営努力によって完済していたので、利兵衛が生活に困ることはなかった。
(すごい女だった。千歳が私の嫁になっていたら木曾屋の経営は彼女が仕切っていただろう。)
千鳥(千歳)は宿場女郎を抱える飯盛旅籠の問題点を正確に把握していた。
幕府の公用交通を安い賃銭で請負わされる宿場の運営は常にカツカツであった。宿場にとっても女郎の数がもろに客数に影響するので、いかに幕府に規制されても出来る限り沢山女郎を置くことを、黙認というよりは推奨している有り様だった。自然、各宿場間でも宿場内でも過当競争になる。千鳥はそれを逆用した。彼女は敢えて客を取らなかったのだ。
千鳥が店に出た途端柳屋に絶世の美女がいると評判になり、男達が一目見たさに店に押し寄せて来たが、彼女が相手をするのは大店の亭主や豪農など、いわゆる名士達だった。それも実際には宴の饗応をするだけで相手はしない。自分を安売りしないということもあるが、実質経営者である千鳥は客の相手などしていられなかったのである。
彼女は売らない女郎という姿勢を貫いたので、いつしか「たとえ一夜の仮寝にしても一生に一度は共にしたい。」と謳われ、一年を過ぎる頃には街道一の女郎と評判となった。彼女は客を軽んじていたわけではない。店の女郎の賃金を上げて意欲を引き出し、腕の良い料理人を雇い料理の質を上げたり、芸事にこだわったりと接客の質を上げることで、高い料金を払う客を満足させていたのである。名士達は千鳥の才覚に惚れ込んでいたので、応援の意味もあって快く金を使ってくれた。いわゆる「通」の人たちだった。そうした人たちの支持もあって、柳屋は2年も経たずに借金を完済したのだ。
そして千鳥に負けないぐらい美人の妹の幾も「都鳥」という名で座敷に上がるようになると、ますます評判になり宿場随一の繁盛店にまでなったのである。
第六章 大宮宿
2.柳屋
この章の目次へ主な登場人物

清五郎
大宮宿の材木商「木曾屋」の主人。千歳・幾姉妹の幼馴染。
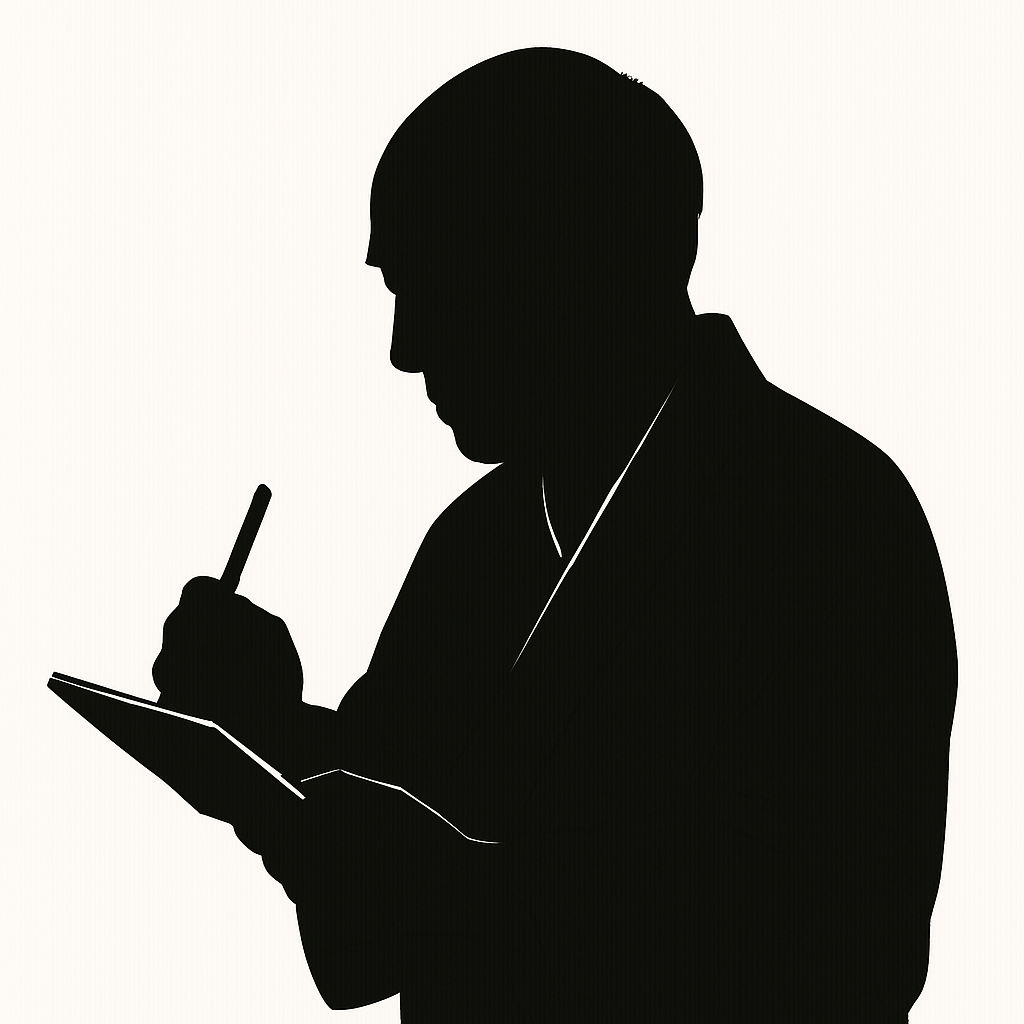
平太夫
清五郎の父で、材木商「木曾屋」の前主人。

千歳(千鳥)
清五郎の許嫁だった女性。恩義を返すために飯盛旅籠を女将兼女郎として再建し、評判となるが自死した。
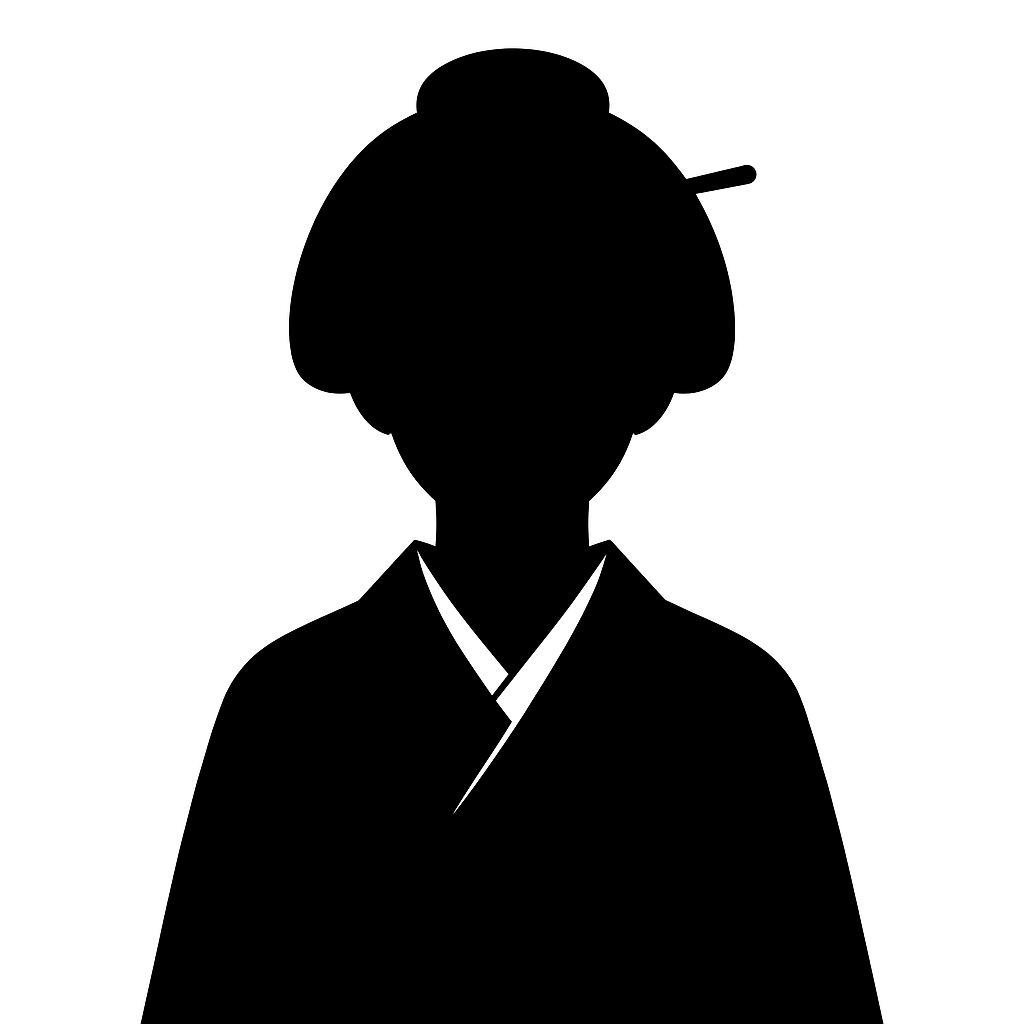
幾(都鳥)
千歳の妹。姉と共に柳屋で育ち、後に女郎として働くが2年前から行方不明。
×