2.杉浦五大夫勝定
平蔵一行が本所牢屋敷に着くと伊奈家家臣の古川弥平次が出迎えた。
「お待ちしておりました、長谷川様。取締役の古川と申します。此度はわざわざ御足労いただき、誠に恐縮に存じます。」
古川は平蔵の突然の訪問にもかかわらず丁寧に平伏した。彼は本所牢屋敷の責任者であった。
「こちらこそ無理を言って申し訳ない。ご迷惑をお掛けします。」
内藤数馬も丁寧に応じた。平蔵は初めて見る本所牢が珍しいのかキョロキョロと屋敷内を見回している。
「不浄の罪人を収監しておりますゆえ、むさくるしい所ではございますが、茶菓子などを用意しておりますので、ささ、どうぞ奥へ。」
古川はそう言って平蔵たちを詰所に促した。
「いや、当方は用事が済み次第引き取りますゆえ、どうかお気遣いなく。」
数馬がそう言って断ろうとすると後ろから平蔵が、
「数馬、先方がもてなしてくれると云うんだ。せっかくだから馳走になろうぜ。なぁ古川殿。」
と言いながら古川の後を付いて行ってしまった。
「ちょっとお頭!」
数馬は慌てて後を追った。
詰所の前には小柄な老人が待っていた。老人は平蔵らを見ると、
「伊奈家番頭の杉浦五大夫と申します。本日はこのような穢れた場所にわざわざ御足労いただき、誠に恐縮の至りでございます。」
と慇懃に頭を下げた。
「これはこれは。伊奈家の御番頭がお出迎えとは。かたじけなく存じます。」
平蔵は老人の名が杉浦と聞いて(杉浦って確かあの調書の?)と見当をつけた。
番頭は家老に次ぐ役職で、大名や大身の旗本にある役職である。ことに伊奈家は家康の関東入国以来200年も代官の筆頭を勤める世襲代官で、家禄4千石の他、2万2千石の収入を特権的に与えられている超が付く名門旗本である。火付け盗賊改め長官とはいえ、家禄400石の長谷川家とは比べようもない家柄であった。したがって家臣とはいえ伊奈家番頭ともなると平蔵と同格と言ってもよい。
詰所は場所が場所だけに、何の飾り気のない無味乾燥な造りだったが、意外にも内部は清潔で、応接用の部屋まであった。中に入ったのは平蔵と数馬で、供の者達は外で待たされた。古川が平蔵を上座に座らせると、早速使用人が茶と菓子を持ってきた。
「>神道徳次郎と面会をされたい、とお聞きしましたが。」
杉浦は挨拶もそこそこに用件をただした。
「はい。そうです。此度の検挙には伊奈殿にもご助力を頂きました。あらためて感謝申し上げます。」
平蔵がそう言うのには理由があった。
神道徳次郎は28歳。徳次郎一党は関東及び東北あたりまで数百か所で強盗を働き、金銀を盗み、あらゆる物品を売り捌き、それで得た金を仲間に分配し、残った金で豪遊していたという。また、役人に変装し、御用であると称し、関所や問屋場をすり抜けて、捕吏の追捕を逃れていた。そしてまた、僧や百姓を惨殺したり、けがを負わせたりと、誠に傍若無人、凶悪至極、大胆不敵、神出鬼没の公儀を恐れぬ広域盗賊団だった。関東の民は彼らのせいで恐怖のどん底に落とされた。
徳次郎の逮捕のきっかけは、彼らが根城にしていた大宮宿でさまざまな狼藉を働いたことで大宮宿の名主や商人達が怒り、代官に取り締まってもらうため、彼らの犯罪の証拠を集めたことに発している。調べてみると大宮宿で発生した連続殺人事件や、公儀役人に変装して悪事を働いている容疑などが発覚し、これは噂の北関東を荒らしまくっている強盗団ではないか?と推測した。そして代官などでは到底太刀打ち出来ぬと考えた彼らは、凶悪犯罪専門の取締官である火盗改めの平蔵に密告したのである。
すぐに内偵に入った平蔵の部下たちは徳次郎たちを見張るとともに、彼らの犯罪の証拠集めを始めた。その際、数年前に伊奈家が水戸徳川家の依頼で、北関東の治安を乱す悪党共の取り締まりのために、杉浦五郎右衛門という者を派遣し、ごろつきや犯罪者を一斉検挙したことを知った。そして平蔵は伊奈家にその時の調書の提出を求めたのである。そこには検挙した犯罪者の罪状や各地の被害届、犯罪の手口などが詳細に記録されていたが、その中に窃盗などに手を染める不良グループ達が、急速に組織化されていることが指摘されていた。その後も伊奈家は各地から寄せられる被害届を分析し、どうやらその不良グループが膨張・過激化していることを掴んでいた。平蔵たちはこの調書に基づき、犯罪の手口や容疑者の特徴から、これが大宮で集合離散する徳次郎一党たちの仕業であるという確信を得たのである。徳次郎始めその幹部らが小伝馬町の牢屋敷ではなく、本所牢に収監されているのもこのような経緯によるのである。
「滅相もございません。ひとえに長谷川様の手腕によるもの。当方は資料を提供しただけでございます。」
杉浦はそう謙遜した。
「そういえば、あの調書の作成者が杉浦五郎右衛門という名になっておりましたが。」
平蔵は目の前の人物も杉浦ということで聞いてみた。
「はい。五郎右衛門は私の倅(せがれ)です。」
「おお!そうでしたか。此度の検挙ではあの調書にずいぶん助けられました。詳細にして正確、的確な分析は徳次郎一党逮捕の決め手となりました。」
平蔵は犯罪捜査に一級品の腕を持つ部下たちをも唸らせた調書を書いた杉浦五郎右衛門に会ってみたかったので、その父親が目の前にいるので興奮していた。
「いや、あの件では五郎右衛門にも抜かりがありました。おおよそ不良共の正体を掴んでおきながら検挙に至りませんでした。もう少し時間があれば芽の小さいうちに摘んでおけたものを。」
杉浦は倅の五郎右衛門が捕り方でも何でもなく勘定方(会計係)であること。水戸様からの依頼が急であったこと。公務の都合上1か月しか出張出来なかったことなどの理由で不良集団の検挙に至らなかったことを詫びた。
平蔵と数馬は唖然として顔を見合わせた。
(1か月だと!?水戸から上州(群馬県)まで大勢の悪党を追い回して逮捕して、北関東全域の犯罪記録の収拾までして1か月だと!?それに勘定方だと!?)
平蔵が驚くのも無理はない。犯罪捜査専門の自分たちでさえ下手人の検挙に何か月も掛かるのに、杉浦五郎右衛門はただの勘定方にして1か月でそれ以上の仕事をやっているのである。
「なにぶん当家は年貢を取るのが本職なもので。それに(老中)や御親藩家から命令でもなければ、領地をまたがる捕り物は出来ないものですから。」
杉浦は申し訳なさそうに言った。
「いやいや、ご謙遜なされるな。そのようなお立場であそこまで。誠に驚嘆に値しますぞ。」
「そうですかのう。」
杉浦五大夫にはそれが当然だと思っているように見えた。
平蔵は未知の力を有した伊奈家の秘密に興味津々となった。そういえば伊奈家は9年前の上州絹一揆も解決している。上州の絹の販売に対する課税事務所の設置に端を発した一揆だが、一揆側の勢いに押され高崎城が包囲されるという未聞の事態に発展した。流血不可避に思えたが、幕閣は事態の収拾を伊奈家に命じると、彼らはあっという間に一揆を沈めてしまった。また、25年前には中山道の伝馬騒動も解決している。これは街道筋の村々が度重なる臨時税に耐えかねて爆発した一揆で、20万人の群衆が増税撤回を求めて江戸を目指したことから、幕府を揺るがす大騒動に発展した。幕府は何人もの使者を派遣して増税撤回を伝えるが、一揆勢は止まることなく江戸に迫っていった。幕府は最後の切札として伊奈半左衛門忠宥(ただおき)に収拾を命じた。桶川宿に急行した伊奈家家臣たちが一揆勢を説得すると「伊奈様がおっしゃるなら。」とあっさり引き上げていった。この2つの事件の収拾にあたって伊奈は一兵も使っていなかった。伊奈家の関東における影響力をまざまざと見せつけられた事件であった。
「3年前の江戸打ち壊し(米騒動)の時の対応もお見事でした。あの時は私も暴徒鎮圧に出動しましたが、彼らは一向に収まる気配はなく、このまま内乱になるのでは?と思いました。それを伊奈殿が乗り出すとあっという間に収めてしまわれた。まるで手品を見ているようでした。」
平蔵は江戸打ち壊しの収拾に自らも関わったことから、これを収拾せしめた伊奈の手腕に舌を巻いていた。
江戸打ち壊しとは天明7年(1787)5月に江戸で発生した暴動で、米不足による米価の暴騰に怒った町人が米問屋などを襲った騒動。この時御先手組の長谷川平蔵も暴徒鎮圧に出動した。そもそもこの天明年間(1781年から1789年)とは異常気象、浅間山の大噴火で農作物に壊滅的な被害が生じ、江戸時代最悪の飢饉になった。特に東北・関東の被害は甚大で、餓死するものが相次ぎ、江戸に流民が押し寄せるなど治安も最悪な状況になっていたという下地があった。そのため何処にも米が無く、大量の米を集めるのは不可能な状況だった。しかし伊奈家はそれが出来た。
彼らは幕府から収拾を命じられると20万両の下賜金を持って諸国から大量の米を集め、江戸町人に廉価で配ったことにより、市中の米価は下がり、騒動は沈静化したのである。この間1か月も掛からなかった。その迅速さ、的確さ、正確さ、公平さにすべての江戸町人は平伏さざるを得なかった。平蔵は知らなかったが、この処理の陣頭指揮を執ったのは目の前の杉浦だった。
「いや、あれは些か(いささか)やりすぎました。」
「やりすぎた?」
「はい。元々米不足なので、地方から米を集めたということは、少ない米を金で右から左に移しただけだからです。そのため地方の小作人から餓死者が出たと聞いています。」
「では、なぜ米を集められたのですか?」
杉浦はそう聞かれると、しばし沈黙した。
「あまり言いたくはないのですが、信用なのです。関東の民は我らを信じております。それは200年間公正無私に農民に接してきた伊奈家の歴史そのものをです。そのため彼らは自分たちの備蓄米以外は進んで差し出してくれました。」
平蔵ははっとした。杉浦が幕政批判しているのではないか?そうでなくともよく思っていないと感じた。つまり幕府に信用が無いから反発が起こると。
「お上がもっと早く対処をしていれば、あの飢饉は被害を少なくできたかもしれません。もっと言えば民衆に飢饉に備えるよう強く喚起していれば、あのような悲惨な状況にならずに済んだと思います。」
杉浦は今度ははっきりと批判した。
平蔵は唸った。幕臣ならばご政道を批判するのは控えるべきだが、この老人は初対面の俺に堂々と語っている。しかも、皆もっともなことである。
(何かある。この人は心に期するものがあるのかも知れない。伊奈家で何かが起こっている。)
しかし、心から民衆を案じているこの老人に、平蔵は親近感を覚えずにはいられなかった。この人なら胸の内を打ち明けても良いのではないか?
「じつは私は江戸に無宿人達の厚生施設を作ろうと思っております。そのための上申書も作成中です。」
「は?武官であるあなたが?何故でしょう?」
「恥ずかしながら私は若い頃は不良でして、町のごろつき達とよく遊んでおりました。だからこそ、彼らが何故犯罪に手を染めるのかよくわかるのです。彼らも本当はそんなことはしたくはありません。原因は貧困、無知によるもので、生きるすべを持っていないのです。私が考える施設は、単に施しをするのではなく、手に職を付けさせ社会復帰を促すものです。真っ当に生きる道を示すことで、彼らに希望を与えられるのではないかと思っております。」
平蔵は忌憚なく打ち明けた。
杉浦はじっと平蔵の眼を見ると嬉しそうに語りかけた。
「良い眼をしていなさる。あなたはきっと優しいのですね。そうですか。そんな施設があれば、世の不幸も減っていくことでしょう。犯罪者のすさんだ心を直すのは難事とは思いますが、あなたなら出来ると思います。」
平蔵は胸が熱くなった。誰に言われるよりも心強いと思った。
「ありがたきお言葉。千万の援軍を得た気持ちです。杉浦殿。この挙に対して何か助言はありますか?」
杉浦は即答した。
「心を尽くすことです。」
その後少しの雑談の後、杉浦は所用があると帰っていった。平蔵と内藤数馬は興奮冷めやらぬ面持ちで杉浦について語った。
「すごい人でしたね!あの人は相当なつわものですよ。」
「ああ、戦国武将を見ているようだった。」
平蔵は何故米騒動の収拾を伊奈家が命じられたか今日分かった。本来それは幕府の財政および農政の長である勘定奉行と江戸町奉行が命じられるべき事案であった。しかし、税金ばかり搾り取る勘定奉行や無宿人や貧民に冷たい町奉行には民の信用が無いのである。伊奈にはそれがある。この民からの信用こそ伊奈家の力の源泉なのだ。伊奈の後ろには関東数十万の民がいる。しかし、と平蔵は思う。
(勘定奉行や町奉行はおろか、幕閣(老中たち)も面白くないだろうな。)
「関東全ての民が味方なら捕り物など造作もないことなんですね。もし伊奈様に兵力があれば、、。」
そう言いかけた数馬を平蔵は手で制した。そして人差し指を口に当てた。数馬もはっとして、まずい事を言いかけたと気が付いた。民衆の支持と軍事力が結び付けば脅威となる。伊奈家に限ってそんなことはないと思うが、その可能性があるというだけで上に立つ者は安心できないのだ。
(なるほど。民衆の側に立つという矜持は一歩間違えば粛清の対象になる。その危うい境界線の上で伊奈家は200年もバランスを取ってきたのだ。杉浦のような強者が育つはずである。)
平蔵は政治権力の難しさに唸った。
第一章 本所牢屋敷
2.杉浦五大夫勝定
この章の目次へこの章の登場人物

杉浦五大夫勝定
関東郡代伊奈家の重臣、番頭。
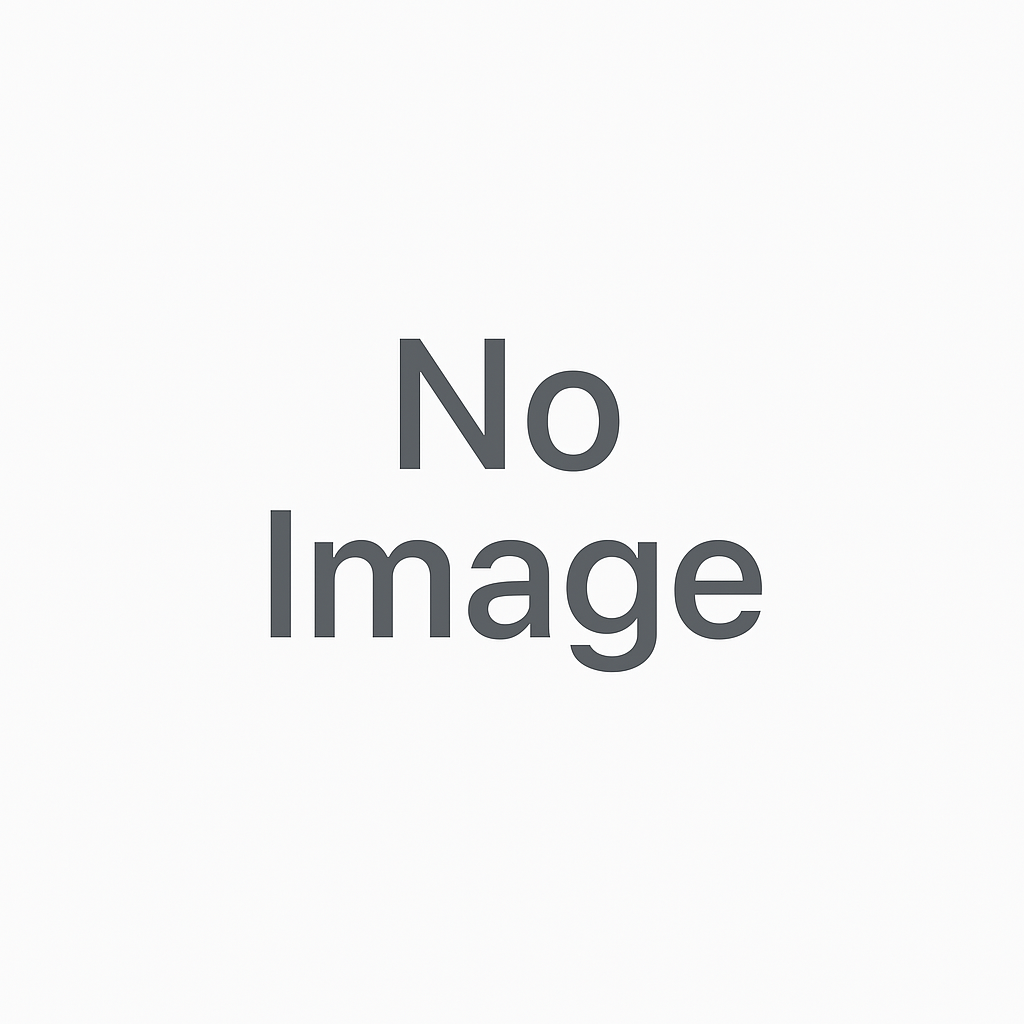
古川弥平次
伊奈家家臣。本所牢屋敷の責任者。

長谷川平蔵
火付盗賊改方長官。先ほど本所牢屋敷に訪問してきた。
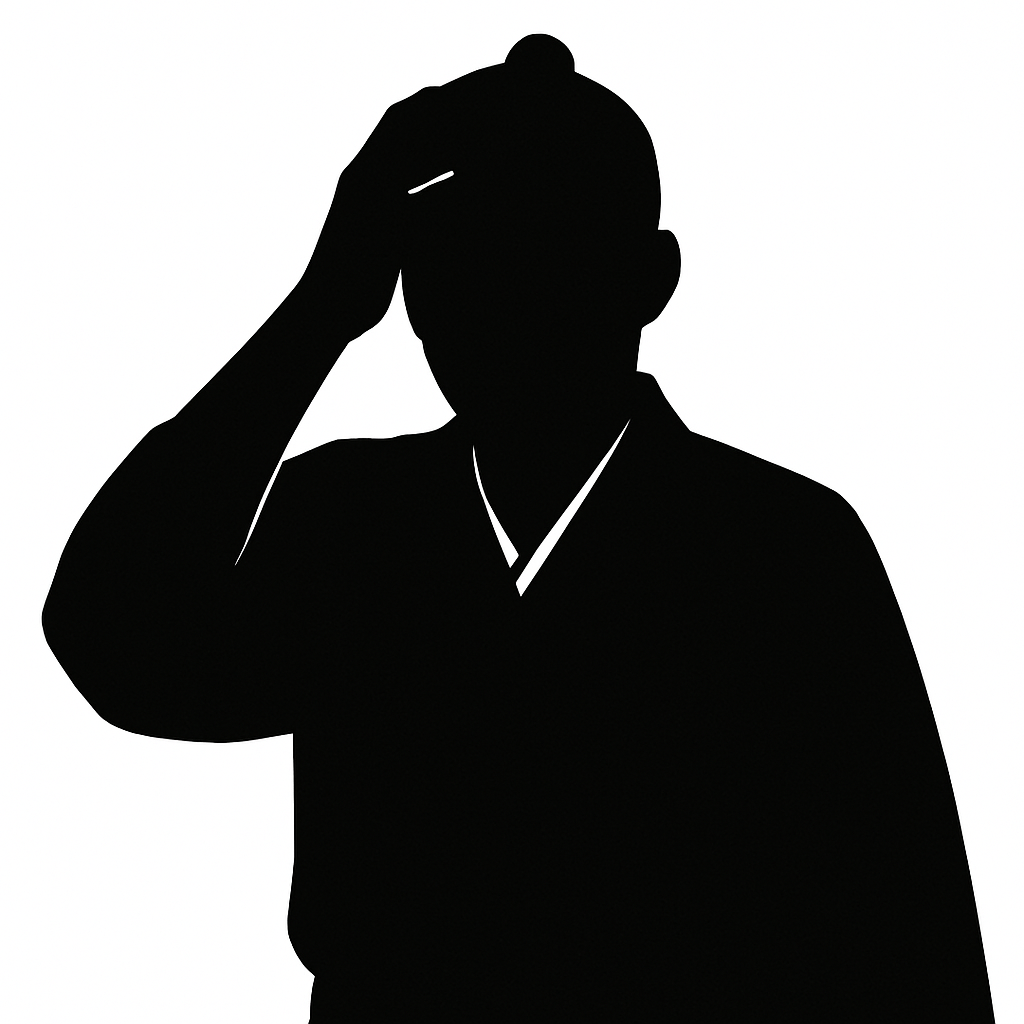
内藤数馬
火付盗賊改方の与力。平蔵の部下。
×