1.長谷川平蔵宣以
本所深川は江戸初期には利根川・荒川の河口で、氾濫常襲地帯であるため、およそ人が住める土地ではなかったが、それが利根川と荒川をそれぞれ東と西に付け替える大工事を幕府が行い、水害の憂いを除くことで村落の形成が可能となった。さらに明暦の大火で江戸の大半が灰燼に帰したことで大規模な都市再編が必要となったため、墨田川以東の本所深川地域を埋め立てし、江戸府内に組み入れることで急速に都市化が進んだ。
寛政元年5月6日、長谷川平蔵宣以は本所菊川町の役宅から供の者を引き連れて同じ本所松坂町の関東郡代伊奈家の管理する牢屋敷に向かっていた。江戸には罪人を収容する牢屋敷が二つあり、一つは町奉行所管理の小伝馬町の牢屋敷で、もう一つが伊奈家の本所牢屋敷であった。それぞれ扱う罪人が違っており、小伝馬町の方は江戸で犯罪を犯した罪人(武士や僧侶も含まれる)で。本所の方は関東郡代伊奈家の支配する30万石の下にいる代官支配地の百姓達であった。伊奈家が独自に牢屋敷を持っていたのは、それだけ対象地域が広大だったからである。
長谷川平蔵は天明6年(1786年)、幕府常備軍精鋭の御先手組弓頭に任ぜられ、昨年10月に加役(かやく、兼任する)として火付盗賊改方長官に就任していた。平蔵は現在44歳である。火付盗賊改(ひつけとうぞくあらため)というのは火付(放火)、盗賊(強盗団)といった凶悪犯罪専門の取締官で、代々御先手組頭が兼務している。江戸の治安は町奉行所が取り締まっていたが、彼らはあくまで警察官。コソ泥や殺人犯を捕まえることもあれば、民事訴訟を裁くこともある民生官だった。江戸時代も中期になると凶悪で広域、しかも武装した組織犯罪が増えてきた。それらは往々にして証拠隠滅のために放火することが多かったので、町奉行では対処しきれなくなった。火盗改めはそれに対応するために作られた組織だった。おのずと捜査や取り調べが荒っぽくなり、幕府内や庶民から嫌われたりもした。
本所牢に向かう道すがら、馬上の平蔵は顔見知りに会うと気さくに声を掛けた。平蔵は若いころは名うての不良で「本所の鐵(てつ)」呼ばれと恐れられていて、父がせっせと貯めた財産を遊郭通いや派手な生活で使い果たすなど、放蕩無頼の青年時代を過ごした。したがって顔見知りというのはその筋(やくざ)の者か、元その筋の者だった。彼らも昔は平蔵と悪さをしていたが、今や平蔵は火盗改めの長官。声を掛けられたところで困った顔をするか、聞こえないふりをして通り過ぎるのだった。
「ちぇっ!つれねえ奴らだな。」
平蔵がぶつぶつ言っていると、内藤数馬が笑いながら馬を寄せてきた。
「お頭、連中は逮捕されると思っているんですよ。」
数馬は火付け盗賊改めの与力で、被疑者や証人を取り調べる役人である。
「逮捕なんかするかい!あんな雑魚共。」
平蔵は吐き捨てるように言ったが、内藤には平蔵が殊の外上機嫌に見えた。平蔵は昨日突然本所牢に行くと言い出したが、彼は平蔵から本所牢に行く理由を聞いてなかったのであらためて聞いてみた。
「今更神道徳次郎に会って何をするつもりです?」
神道徳次郎とは先月大宮宿で平蔵が捕縛した大盗賊の頭目であり、平蔵の本所菊川町の役宅で取り調べが済んだ後、本所牢に移送され沙汰を待っている罪人である。
「まあ、いろいろとな。一つは昨日お上から徳次郎の処分を内々に教えてもらっただろ?それを本人に直接伝えてやろうと思ってな。」
「梟首(きょうしゅ:獄門、さらし首)でしたな。しかし、そんなことのために?」
「もう一つは感謝を伝えようと思ってよ。」
平蔵は火盗改めに就任してから、今まで目立った活躍が無かったが、当代きっての大盗賊、神道徳次郎一味を捕まえたことで大いに名を挙げた。その意味では徳次郎は恩人と言えたが。
「お頭も人が悪い。」
数馬は平蔵の悪趣味にあきれた。
「まだあるが、とにかく奴には言いてえことがたくさんあるんだ。」
そうこう言っているうちに本所牢が見えた。平蔵の役宅から目と鼻の先と言っていいくらいの距離である。
「ほれ、もう着いたぞ。」
第一章 本所牢屋敷
寛政元年(1789)5月6日
1.長谷川平蔵宣以(のぶため)
この章の目次へ主な登場人物

長谷川平蔵宣以
火付盗賊改方長官。かつては本所の鐵と呼ばれる不良だった。44歳。
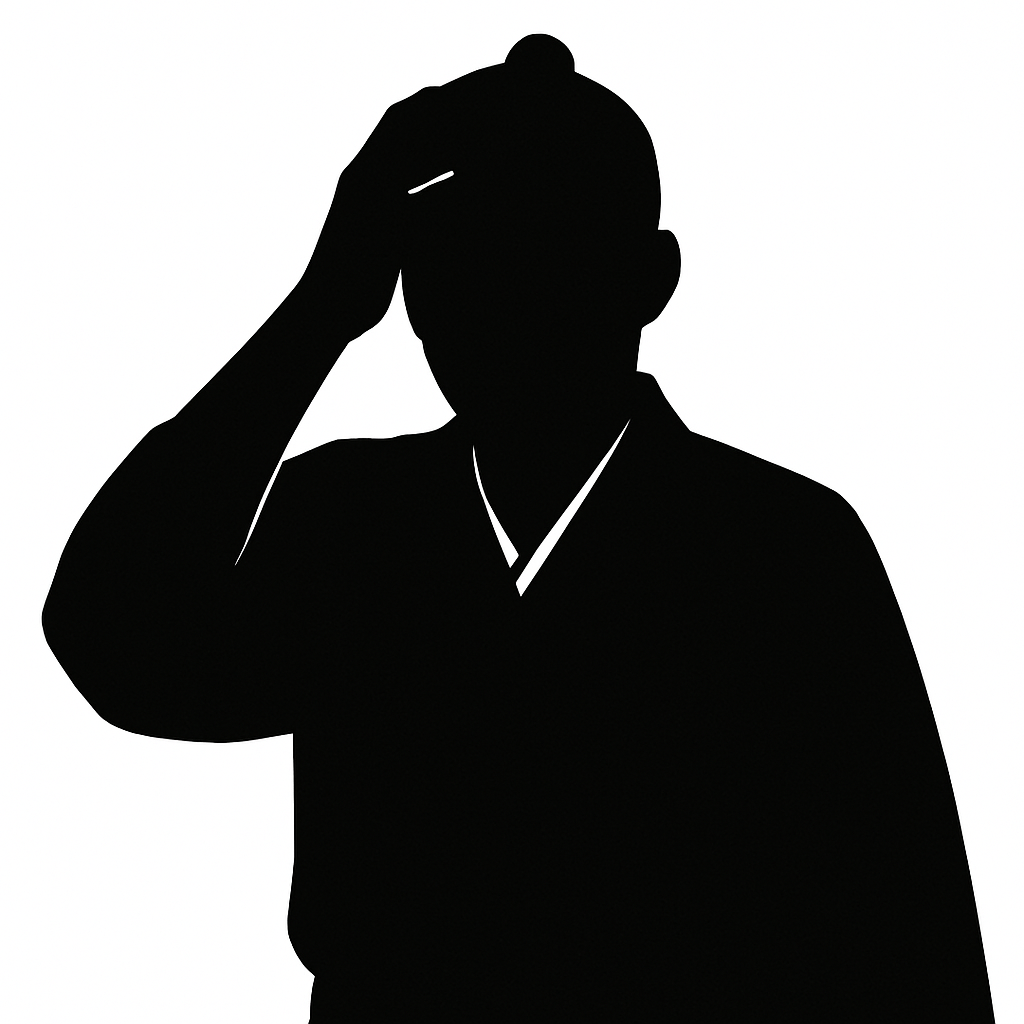
内藤数馬
火付盗賊改方の与力。平蔵の部下。

神道徳次郎
大盗賊の頭目。先月大宮宿で平蔵に捕まる。